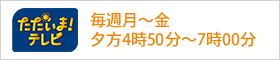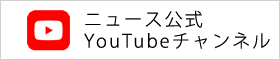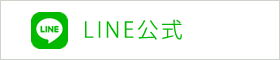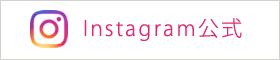救えたはずの命を守る 避難所の福祉支援整備 南海トラフ地震に備える私たちが取り組むべきこと

テレビ静岡
2024年1月に起きた能登半島地震では、建物の倒壊や津波から逃れても、避難所で命を落す人が相次ぎました。南海トラフ地震に備える私たちが、取り組むべきことを考えます。
【動画】救えたはずの命を守る 避難所の福祉支援整備 南海トラフ地震に備える私たちが取り組むべきこと名古屋大学・福和信夫 名誉教授(ワーキンググループ主査):
何としても、南海トラフ地震の被害を減らさない限り、この国の将来が非常に危ぶまれると感じておりまして、そろそろ本気になって対策に取り組んでいただきたい
2025年3月。
南海トラフ巨大地震の新たな想定を示した専門家は強い危機感を表し、本気になって対策に取り組むよう訴えました。
激しい揺れと巨大な津波…さまざまな備えが必要になる中、改善が急がれる対策、その一つが 「避難所の体制整備」です。
避難生活などで命を落とす災害関連死は、能登半島地震で直接死の1.5倍以上の372人となる見通しで、東日本大震災では3808人に上っています。
加藤洋司 解説委員:
自宅の損壊やライフラインの断絶で、どれ位の人が避難をしたのか?避難するのか?能登半島地震の5万2000人や、東日本大震災の47万人と比べると南海トラフ巨大地震の1230万人と、いかにケタはずれかが分かります。どれだけ厳しい現実があるのか、それは能登半島地震にも見て取れます
静岡県立大学・短期大学部で、社会福祉を研究する鈴木俊文 教授は、能登半島地震の発生後、現地に入りました。
福祉の専門チーム、静岡DWATのアドバイザーとして、高齢者・障害者、妊婦など誰もが安心して過ごせる避難所の体制整備に力を尽くしました。
いま何より必要と感じることは…。
静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科
鈴木俊文 教授:
避難というのは、津波が来たから逃げるということが避難ではなくて、避難生活というかなり長い期間が想定されることを次に考えておくことが大事
2024年1月に能登半島を襲ったマグニチュード7.6、最大震度7の地震。
寒さの厳しい季節、多くの人が元日に突然、それまでの日常を失いました。
輪島市で被災した平田真由美さんは、母親のあつ子さんを亡くしました。
足が不自由で自力で避難できなかった母親は1月3日に自衛隊に救出され、避難所に身を寄せました。
そこで容態が急変し、その2日後に病院で息を引き取りました。
死因は低体温症でした。
平田真由美さん:
いつも寒がらないお母さんが寒がって、低体温症になっていて、物資とかも何もなかった。布団、毛布もなかった。準備もしていなかったし
宮城県から支援に入った医師は…。
石巻赤十字病院・植田信策 医師:
床っていうのは、どんどん体温が奪われて行くんですよね。そうやって温度が奪われて行って低体温になりやすいということ。食事も十分な食事がとれないと、体温を作れないということがあります。土足のまま雑魚寝している。東日本大震災と基本的に変わっていないことがショックでした
被災者がまず身を寄せる学校や公民館は1次避難所と呼ばれます。
これに対し、ライフラインの整ったホテルや旅館は2次避難所と呼ばれます。
地震のあと、石川県が力を入れていたのが、1次と2次の間に位置付けた“1.5次避難所”の開設です。
金沢市にあるスポーツ施設には250のテントが用意されました。
石川県・馳浩 知事:
続々とこちらに送って頂いて、劣悪な環境を少しでも改善したい
施設が開設された1月8日、静岡県立大の鈴木さんも現地に入りました。
介護福祉士や保育士、心理士などでつくる災害福祉支援チーム・DWATの役割は、配慮が必要な人の心身の状態の聞き取りや避難所の環境改善です。
静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科
鈴木俊文 教授:
日頃ベッドで、自宅で寝ている人が体育館で寝るとなった場合、床から立ち上がる、寝るという動作が伴います。これは簡単な事ではなく高齢者にとって、それ1つが骨折の原因になったりとか、いろいろな問題が生じます
段ボールベッドで動作を少なくし、靴を履き替える場所にはイスを設置します。
不調を口にせず我慢する人もいるため、聞き取りだけでなく観察が重要です。
静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科
鈴木俊文 教授:
歩行が不安定な方で、食事を取りに行くのも難しいということであればトイレに行くのも大変と容易に想像ができて。トイレに行くのが大変と思われる方であれば水分を控えているかもしれないと専門職者は考えます。医療や保険、福祉の支援者が常駐している環境の中で、避難生活を一定期間継続できるということ、この実現は非常に大きかったと思います
4年前に熱海市で起きた土石流災害。
この時にも、静岡DWATは県の要請を受けて現地に入り、被災者の健康状態や孤独に陥っていないかなど状況把握につとめました。
能登半島地震でも延べ59法人の80人が現地に入って被災者を支え、それぞれも多くのことを学ぶ機会となりました。
南海トラフ巨大地震で想定される避難者は全国で最大1230万人、県内では159万人。
2.2人に1人の計算です。
鈴木さんは福祉施設同士の連携や地域での重層的な支え合いが重要で、ひとりひとりには訓練や講座などを通し、定期的に防災について考えることが大切と話します。
避難所の運営ゲームも効果的なシミュレーションになります。
静岡県立大学 短期大学部 社会福祉学科
鈴木俊文 教授:
1~2日で終わる訳ではなく、1週間・2週間・3週間と続くわけです。本気で考えるべきなのは初動として逃げるところと、避難生活をして長期化する場合にどのように対応するか。2つをそれぞれの立場で考えていかないといけないと強く思っています
揺れ・津波が収まったら終わりではありません。
救えたはずの命、助かるべき命を守るため、本気になった対策がいま強く求められています。