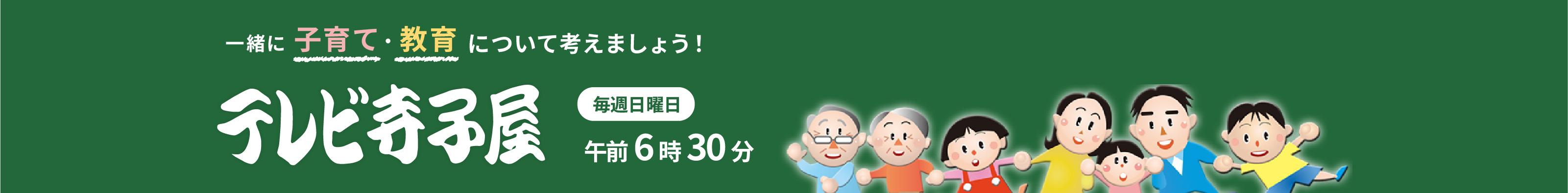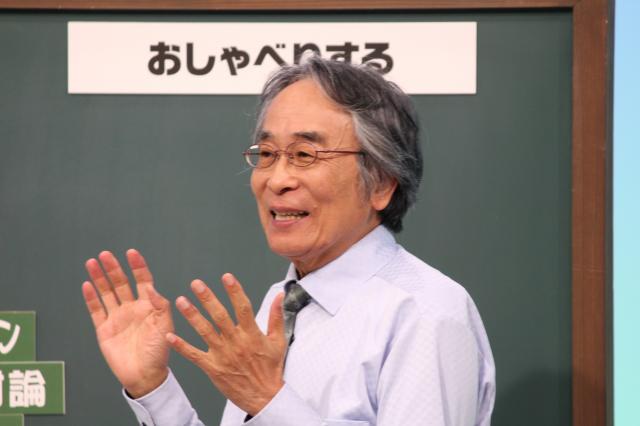
2025年8月24日放送
- 会場
- テレビ静岡(静岡市)
- 講師
- 教育評論家 親野智可等
プロフィール
1958年静岡県生まれ。公立小学校で23年間教師を務める。
教育現場で親が子どもに与える影響の大きさを痛感。
教師としての経験と知識を子育てに役立ててもらいたいとメールマガジン「親力で決まる子供の将来」を発刊し、評判となる。
第 2446 回
自己肯定感の高め方
「自己肯定感」とは、「自分の存在そのものを丸ごと肯定する感覚」で、長所だけでなく短所も含めて「自分は今のままでいい」「自分のことが大好き」とありのままの自分を肯定する感情のことです。自分らしく豊かな人生を送るために大切なものですが、どうすれば子どもの自己肯定感を育むことができるのでしょうか。
最初のポイントは「子どもは毎日、脳天気なほど楽しくていい」です。
毎日楽しく笑って過ごしていると、子どもはこう思います。「楽しいな、幸せだな、自分はここにいていいんだ」つまり、自己肯定感が上がるんです。最近注目されているのが「ハピネスアドバンテージ」=「幸せな状態は有利」という概念で、「子どもが学校で楽しく過ごせていると、勉強への集中力が上がって、学力も上がる」という研究結果もあります。これをぜひ、しつけの面でも活用してほしいと思います。例えば、子どもが朝起きてこないときや、片付けをさせたいとき、親はついつい叱りがちですが、歌・踊り・ゲーム的要素などを取り入れたりして、ぜひ楽しくて笑えるような、叱らなくてもすむ工夫を心がけてみてください。
次のポイントは「子どもへのいじりをやめる」。
子どもが可愛くて笑わそうと思って、いじったり、からかったりしてしまうことがあるかもしれません。たとえ親に悪気がなくても、子どもはそれによって深く傷つき、親に対する不信感が募ったり、自己肯定感が下がったりします。大人になっても、子どもの頃に言われたことを引きずっているケースも多いので、これは本当にやめていただきたいと思います。
そして、もうひとつ気を付けたいのが「感情のコントロール」です。子どもの自己肯定感を上げようと努力しても、親がストレスを我慢できず、子どもにぶつけてしまっては全てを台無しにしかねません。相手を嫌な気持ちにさせない方法でストレスを発散できるといいですよね。
例えば、私が小学校の教員時代に子どもたちとやっていたのが「犬語でケンカ」。これは、相手に触らない約束で、隣の人と「ワンワンワン!ウー!」といった犬語でケンカするというものです。意味を持たない鳴き声だから相手を傷つけず、すごくストレス発散になって、お互いに笑ってしまうほど盛り上がりますよ。ぜひ親子で実践してみてください。
最後に「親子ともども、幸せ体質になろう」。
笑って楽しく毎日を過ごしていると、自己肯定感がどんどん上がり、幸せホルモンが出やすい「幸せ体質」になります。「将来」というのは形あるものではなくて、今この時まさに現在進行で「将来」を作っています。ですから、今この時を親子で楽しく幸せに過ごしていたら「幸せ体質」になって、その延長線上にある将来も、子どもは自然と「自己肯定感」を持ち、楽しく幸せに生きていけると思います。