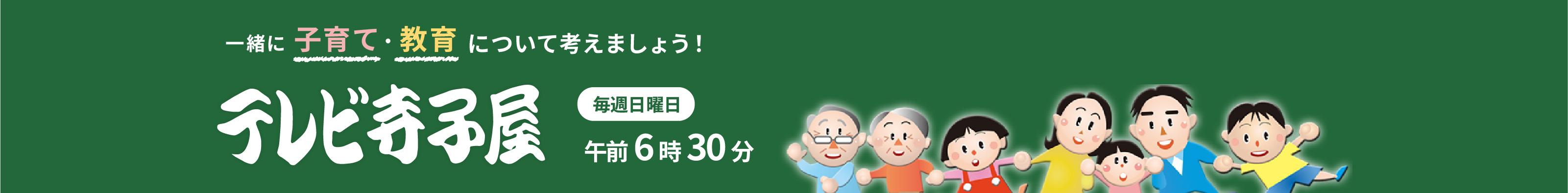2025年1月19日放送
- 会場
- 沼津市民文化センター(沼津市)
- 講師
- 明治大学文学部教授 齋藤孝
プロフィール
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、同大学院教育学研究科博士課程等を経て現職。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。
「声に出して読みたい日本語」ほか、著書多数。
第 2415 回
「実語教」に学ぶ大切な智恵
「学ぶ」というのは、今まで知らなかったこと、先人が与えてくれた知識を「そういうことなんだ」と知ることが基本です。「学ぶ」があると人生が、柱がちゃんと立った家になる。「学ぶ」が大黒柱になるということですね。
江戸時代に教育を受けている人たちにとって常識だった『実語教』というものがあります。平安の終わりに成立し、鎌倉、室町と続き、江戸時代には寺子屋の教科書になりました。学びの大切さや礼儀など、世の中で人間が生きていくうえで欠かせない大切な智恵が詰まっていて、私は「日本人千年の教科書」と呼んでいます。どういうものなのか、少し具体的に紹介しましょう。
最初に出てくるのが、『実語教』で一番有名な言葉です。
『山高きが故に貴(たっと)からず。樹有るを以て貴しとす。人肥たるが故に貴からず。智有るを以て貴しとす。』
山は高いからといって価値があるわけじゃなく、木があるから価値があるんだ。それと同じように人間は、おいしいものを食べて肥えていることで尊いのではない、智があることによって尊いのだ。これを江戸時代の子どもは覚えたんです。何度も復唱しながら暗唱することで自分の言葉のように胸に刻み込みます。すると、ふとした瞬間に湧き上がってきて、自分に影響を与えるんですね。
次に紹介する言葉は、
『老いたるを敬うは父母の如し。幼(いとけなき)を愛するは子弟の如し。我他人を敬えば、他人また我を敬う。己(おのれ)人の親を敬えば、人また己が親を敬う。』
自分が他人の親を敬うと、他人も自分の親を敬ってくれる。人のことを敬うと、自分に返ってくる。「情けは人のためならず」という似たことわざがありますね。人のためならずというのは、巡り巡って自分にも返ってくる。まず自分がやってみようということですね。例えば、苦手な人に会った時、「あ、見なかったことにしよう」ではいつまでたっても苦手になってしまうので、「あ、どうも」みたいに自分から声をかけるんです。すると、相手もこっちに良い感情を持ってくれます。自分のことを好きな人を嫌いにはなれません。相手を敬い自分からアクションを起こして、人の世を丸くしていくということです。
最後に、この『実語教』の終わりの言葉を紹介します。
『これ学問の始め、身終わるまで亡失することなかれ。』
この書を読むことが学ぶことの第一歩。実語教は寺子屋で最初に学ぶ一番優しいものですからね。そして、「一生を終えるまで学ぶことを忘れてはいけません」と、これがシメになります。力強いですよね。学びで一生を貫く。このコツを覚え人生の信条にしたら、もう怖いものは何もないです。最後の日まで勉強し続けると思っていれば、この世はなんて楽しいのでしょう。何を知っても「すごい!すごすぎる!」という気持ちを持つといいですね。すると、「ああ、この世に生まれてよかったなあ」と思えます。
そういう楽しい学びのある人生を送っていきましょう。