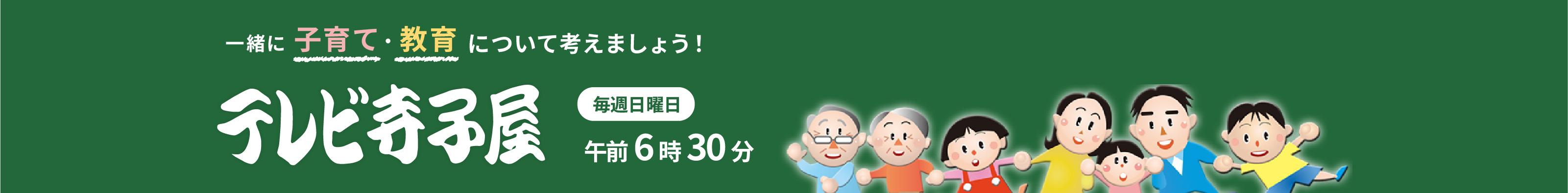2025年2月2日放送
- 会場
- 麁玉小学校(浜松市)
- 講師
- 京都外国語大学教授 ジェフ・バーグランド
プロフィール
1949年米国生まれ。高校教師歴22年と、大学の指導では30年以上のキャリアを誇る。
50年以上京都に住み、京都国際観光大使も務める。
専門は観光と異文化コミュニケーション。
第 2417 回
日本語っていいですね
手の指を組み、左右の親指のどちらが上になっているか見てみてください。私の専門である「異文化コミュニケーション学」の中で数十カ国数十万人にやってもらったところ、だいたい右と左が半々だったそうです。右の親指が上になっているのが僕にとっての正解で、左の親指が上になっている方は、それがその人にとっての正解です。これを「自文化」と言います。我々はあまり自分の文化を意識しないものです。
よくある例えですが、宇宙飛行士が長期間宇宙に滞在すると、帰ってきた瞬間に口から出る言葉は「重力がすごいですね」だそうです。自分の文化から離れて初めて「自文化」を意識する。私は日本に来て、アメリカ文化をずいぶん意識するようになりました。
では、次は上になる指を変えて組んでみてください。1回目に比べ多くの人が自分の手を見て確認したと思います。いわゆる「異文化」と出合ったときに、私たちはそれを意識する、違和感を感じるのです。でも、異文化コミュニケーションでは、この違和感は悪いものではありません。
私にとって異文化である「日本語」について話します。
日本語を学ぶと「省略」が非常に多いことに気づきます。例えば、日本人同士で「見た?」「うん、見たよ」と動詞しか使わない会話をしています。英語では「Did you see it?」と主語や目的語をしっかり出さないとならず、「See?」だけでは成り立ちません。
さらに、私が一番大事な特徴だと思うのが、日本語は「受信者責任型言語」だということです。受信する側が解読しないといけないのです。
具体例として、松尾芭蕉の「枯朶(かれえだ)にからすのとまりけり秋の暮」という俳句があり、日本文学研究者のドナルド・キーンさんがこれを英訳するときに大変だったそうです。英語にするときには「からす」が単数なのか複数なのか、「秋の暮」が日暮れなのか秋の終わりなのかはっきりする必要があります。英語は「発信者責任型言語」、発信する方が責任をもってはっきりしないといけないのです。キーンさんが、「日本語っていいですね、自由自在に読む人が自分で解読したらいいんだ」とすごく大切なことを書いています。
「一を聞いて十を知る」というのは、日本語が受信者責任型コミュニケーションだからです。日本人は世界一の受信力を持っていると思います。これは素晴らしいことです。実は、この日本人が極めてきた受信力というものが、他の文化を吸収していくために大事な力なんです。受け入れる心が大きい。「それもありかな」と否定しない。これが日本人の日本語から来る受信力だと思うのです。
「受信者責任型言語」の日本語は、本当にいいなと思います。