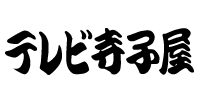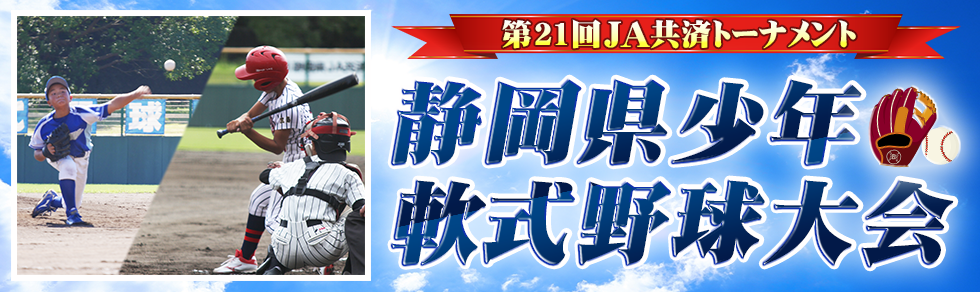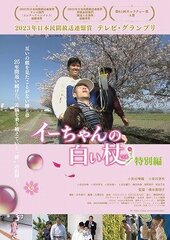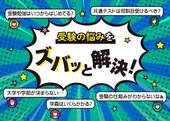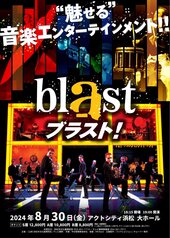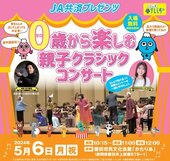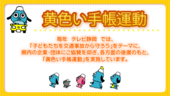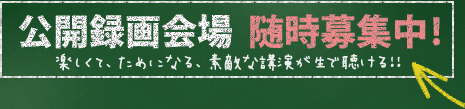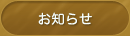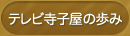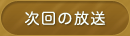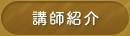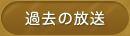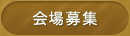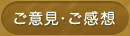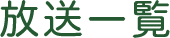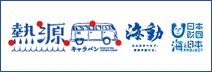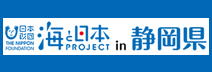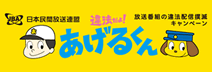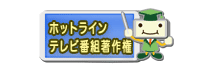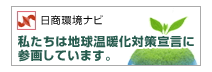2015年7月 5日放送 樹原涼子さん(第1942回)
2015年7月 5日放送 樹原涼子さん(第1942回)

- 会場
- 裾野市生涯学習センター(裾野市)
- 講師
- 音楽教育家 樹原涼子
講師紹介
熊本市生まれ。武蔵野音楽大学卒業。
1991年より順次出版されたメソッド「ピアノランド」がベスト&ロングセラーに。
作曲・執筆の傍ら、セミナーやコンサート、音大での特別講義などを通じ、
ピアノ教育界に新しい提案と実践を続けている。
 第1942回「聴くことの意味」
第1942回「聴くことの意味」
私にとって音楽というもの、
ピアノを弾くということはどんなことかを考えるのに大きな出来事がありました。
震災の時、たくさんの家が流され、多くの命が失われ、またたくさんの楽器も流されました。
ピアノを弾いていた子供も大人も大変な思いをしたことでしょう。
“原(はら)”つながりで“ハラハラクラブ”というユニットを組んでいる小原孝さんと、
震災の直後から、支援コンサートを開いてきました。
また、ピアノランドフェスティバルという、全国の子供たちのための夏のツアーも行い、
寄付金を募り、沢山の電子ピアノを贈ることが出来ました。
活動を通じ、手紙や写真などが送られてきますが、
それまではピアノを弾くことがそんなに好きではなかった子たちがピアノを弾くことで
自分の時間を取り戻した様子が伝わってきます。
親御さんの手紙に「わが子のピアノを聞くは何年ぶりでしょう。
子どものピアノを聞いて、生活が戻ってきたと感じた」というものもありました。
プロジェクトを通して、子どもたちが自己表現をして、
周りを幸せにできたことが音楽のパワーではないかと感じています。
ピアノの音は、一音弾くとだんだんと小さくなっていきます。
ラッパのように途中で大きくはできません。
レッスンでは音のしっぽを聞くようにと教えます。
だんだんと小さくなってゆく音に応じて次の音を弾くことが出来る、
音と音との関係が大事です。
お子さんたちとのレッスンでは
自分の音をよく聴いてから次の音を弾きなさいと言います。
音の尻尾が聞こえるように注意深く聴くのです。
音楽はメロディー、リズム、ハーモニーでできています。
聞き取り術の本は、
日本人の苦手なハーモニー部分を楽しくするために作りました。
卒業式などで流れるC-G7-Cという和音を弾くと
自然にお辞儀がしたくなりませんか?
和音は人の行動を変える力があります。
いろんな表情の和音を知ることは言葉でいえば
漢字を知ることと同じです。
小さな音に耳を澄まし、ディテールを知れば、
ひらがなでなく漢字で表現することと同じように語彙が豊富になるのです。