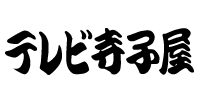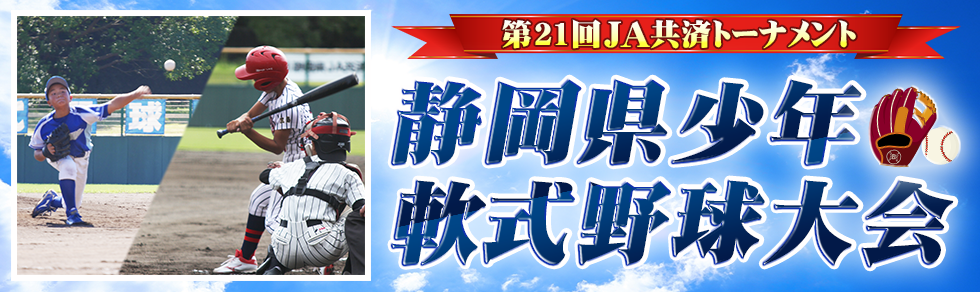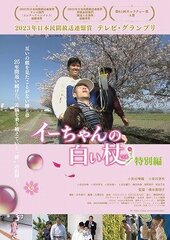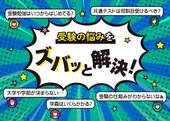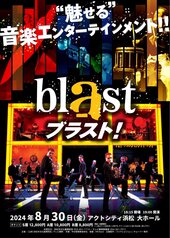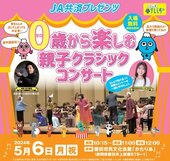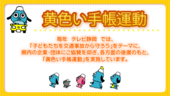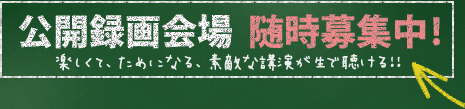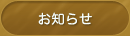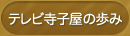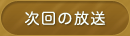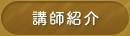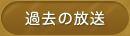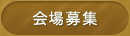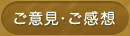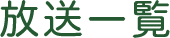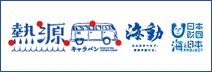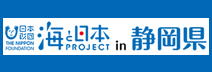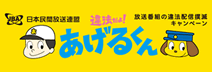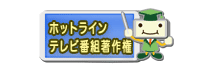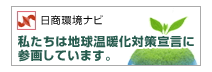2015年7月19日放送 樹原涼子さん(第1944回)
2015年7月19日放送 樹原涼子さん(第1944回)

- 会場
- 裾野市生涯学習センター(裾野市)
- 講師
- 音楽教育家 樹原涼子
講師紹介
熊本市生まれ。武蔵野音楽大学卒業。
1991年より順次出版されたメソッド「ピアノランド」がベスト&ロングセラーに。
作曲・執筆の傍ら、セミナーやコンサート、音大での特別講義などを通じ、
ピアノ教育界に新しい提案と実践を続けている。
番組で紹介した本
「耳を開く 聴き取り術 コード編」 著者:樹原涼子(音楽之友社) 第1944回「心配はご無用!」
第1944回「心配はご無用!」
今日は親御さんの気持について考えてみたいと思います。
心配というものには二通りあって、
一つは病気になった人を見舞うなど、相手を気遣うもの。
もう一つは、子供が、自分の思い通りにならないことへの心配が多いように思います。
若いころ、私の友人の一人が、とても心配性で、好意を抱いていたある男性のことを、
「もし付き合って相手にこんなことを言われたらどうしよう」と、
仮定の話を相談されたことがあります。
私は「付き合ってもいないのにその心配は早い、まず告白したら」と言ったら
「断られたらどうしよう」と言う。
これは個人の人生の中のことなので笑い話にもなりますが、
親が子供に対して同じような心配をしていたら、
子供には負担になるのではないでしょうか。
あるとき、あるお子さんが母親に、
「お母さんは、“あなたが心配だから”と言えば
何を言っても許されると思っているのでしょう」と言う場面を目にしました。
ドキッとしませんか?自分がこうなって欲しいというわが子が、
そこから外れると嫌だ。つまり自分の心配をしているのです。
その子は論理的に自分でちゃんと伝えられましたが、
未熟なためにそれを言えない子の場合は、行動が乱暴になったり、
引きこもりになったりするかも知れません。
心配することは“いいこと”で、“親だから当たり前”でしょうか?
心配の方向性を変えることが必要なのではないでしょうか。
それには主語をたどってみるといいのです。
あの子のことが心配→誰が?→私が。
では、あの子は心配してほしいのか?あの子は心配しているのか?
あの子の心配と私の心配とはどう違うのか?と、心配の中身をきちんと考えてみると、
一方的に子供に対してワァーッと言わなくても済むのではないでしょうか?
最終的に、子どもに決定する権利がない場合、
子どもはとても無力感を感じてしまいます。
大好きな親を悲しませたくないとギリギリまで頑張ってしまう子が多いのですが、
もしかすると心の中には小さくても別の世界が広がっているかも知れません。
心配、やめませんか?
そのためにどうすればいいか?
信頼し応援することです。
勉強してほしい時も放っておくと、自分らしく計画し、
自分で自分の舵とりを始めるようになると思います。