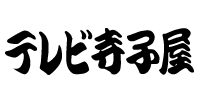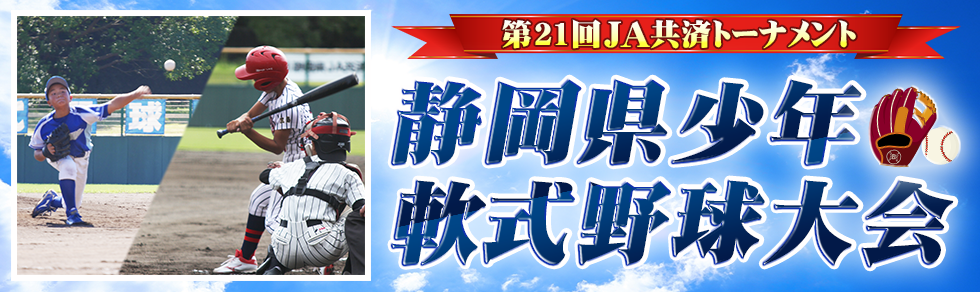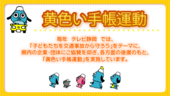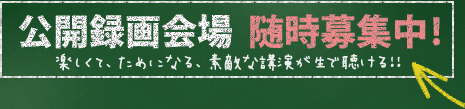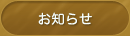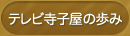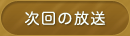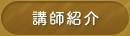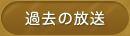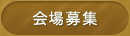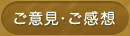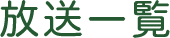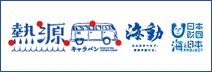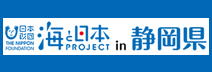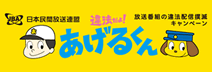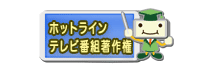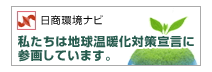2022年12月11日放送 汐見稔幸さん(第2310回)
2022年12月11日放送 汐見稔幸さん(第2310回)
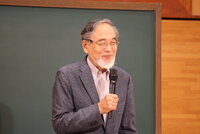
- 会場
- 御殿場市民交流センターふじざくら(御殿場市)
- 講師
- 東京大学名誉教授 汐見稔幸
講師紹介
1947年大阪府生まれ。日本保育学会会長や
白梅学園大学学長などを歴任。ぐうたら村村長。
専門は教育人間学、保育学、育児学。
現代の父親、母親の育児の応援団長をめざしている。
番組で紹介した本
「教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと」 著:汐見稔幸(河出書房新社) 第2310回「教えから学びへ」
第2310回「教えから学びへ」
いま世界の国々で教育が大きく変わろうとしています。「どう教えるか」に重点を置いた教育ではなく、子どもたちの学びをどう支えていくか。「教え」よりもむしろ「学び」の応援を重視した教育が求められています。20世紀型の教育から、子どもを主人公にした21世紀型の教育に変わりつつあります。
私たちは学校で教科書に載っていることを覚えて、テストの点数で評価されてきました。正解を覚えることや正しい知識を身につけることが教育でした。しかし、学校で教えてもらったことで大人になってから役に立つことがどのくらいあるでしょうか?「二次方程式の解の公式」が日常生活に役立っていますか?私たちはそういった教育を受けてきて、特にそれを疑問には思いませんでした。
しかしインターネットが普及し、子どもたちもスマートフォンを持つ時代になりました。30年前には想像もできなかったことです。現在の社会は変化が早く、知識の量もどんどん増えています。ブーカ(VUCA)の時代、「先行きが不透明で将来の予測が困難な状態」といわれます。学校で子どもたちに何を教えればいいのか?教えるべき「知識」や「答え」を選ぶのさえ難しい時代です。知識を伝え、それを理解して記憶するという「20世紀型の教育」の成り立ちも危うくなっています。
情報を手に入れるためのツールも発達しました。学校の教科書で教わらなくても、いろいろなことが学べるようになりました。書店が苦戦する時代にも関わらず、子ども用の図鑑は売り上げを伸ばしています。子どもたちは何かに興味を持ったら自分で図鑑を見て覚えます。それ以外にもインターネットの情報、動画コンテンツなど、知識を身につけたり学んだりするツールは多様化しています。学校で先生から教わることより、メディアを使った方がより広く、深く学べることもある。20世紀型の教育に対して子どもたちが魅力を感じられない時代になっています。
私は鉄腕アトムに憧れた世代です。科学技術が発達すればみんなが幸せになるという思いや夢がありました。しかし、この発展した技術が「自然」に大きな影響を与えてきたことも否めません。気候変動や温暖化など、環境問題も危惧されています。いまの子どもたちは、こうした諸課題を解決する力が求められる世代です。授業でソーラー発電や風力発電のアイデアを出し合ったり、ユニークな風車づくりに取り組んでみたりしたら学校がおもしろくなります。既成の知識を教わり、それを覚える教育から、「新しいアイデアを出し合って実際に形にする教育」に切り替えていく。そうすれば彼らが大人になった時、問題を解決する答えを導き出し、自ら実践していく力が身につくでしょう。
これまでの「教える教育」から子どもたちの豊かな「学びを支えて応援する教育」へ。家庭でも子どもが興味を持ったものを伸ばしてあげてください。そして子どもを信頼し、自分探しを応援してあげてください。